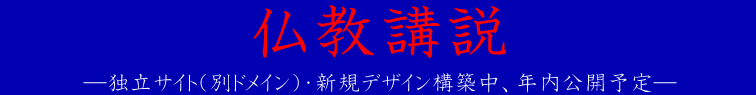
現在の位置
‡ 説一切有部の心所説 ―仏教における心の分析
分別説部の心所説 | 説一切有部の心所説 | 瑜伽行唯識の心所説
1.説一切有部が主張する究極的実在
説一切有部
釈尊ご入滅後、幾ばくかの時を経て形成されていった部派仏教(Sectarian Buddhism)と現代に呼称される仏教諸派の中でも、特に北・中インドで最大の勢力を有していたものに、説一切有部[せついっさいうぶ](Sarvāstivādin)という部派があります。この部派にはまた、説因部[せついんぶ]との異称もあります。
伝承によれば、尊者Kātyāyanīputra[カートヤーヤニープトラ](漢訳名は迦多衍尼子[かたえんにし])というバラモン出身の学僧によって立てられた部派と伝えられています。正確な尊者の生没年は不明です。が、仏滅後二百年を過ぎたころに生を受け、(根本)上座部で出家し頭角を現していたものの、やがてそこから説一切有部を分出するに至った、と伝承されています。
実際、説一切有部の成立そのものについての伝承も、仏滅後二百年から三百年の間で、しかもその早い時期にあったとされています。
(説一切有部の成立について触れている項に、“部派仏教 ―説一切有部の僧伽分裂説”がある。参照せよ。)
さて、その説一切有部の教学の勝れた綱要書に、Abhidhrmakośa[アビダルマコーシャ]という、サンスクリットで著され、また漢訳そしてチベット訳され伝えられてきたものがあります。
書名にあるAbhidhrma[アビダルマ]とは、ふつう阿毘達磨と音写され、また「対法」などと漢訳されますが、「涅槃に向かわしめる教え」、あるいは「真実を対観する教え」を意味するものとされます。kośa[コーシャ]とは、「樽」や「蔵」、あるいは「箱」など容器を意味する語です。漢訳本の書名は『阿毘達磨倶舎論[あびだつまくしゃろん]』と訳されず音写されており、我々は普通これをただ『倶舎論』と略称しています。なおチベット訳の書名は、Chos mṅor paḥi mdsod-kyi bśad-pa。
これは、四世紀中頃の西北インド・ガンダーラ、現在で云えばアフガニスタンのペシャワールのバラモン階級出身の学僧、Vasubandhu[ヴァスバンドゥ](漢訳名は世親[せしん])によって著された書です。説一切有部の教学をかなり批判的に扱って時に反駁を加えながら、しかしその要を組織的に、そして簡潔にまとめている非常に勝れた書です。
しかし、この書を著して後、著者の世親は、同じく上座部系の化地部で出家していたものの、すでに大乗に転向していた兄のAsaṅga[アサンガ](漢訳名は無著[むじゃく])の影響によって、説一切有部(あるいは経量部)の見解を捨てて大乗に転向しています。
そして、大乗の二大学派の一つとなる瑜伽行唯識[ゆがぎょう ゆいしき]という学派を、兄と共に建立。そのようなこともあって、大乗の学徒は、これら二人を尊敬を込めて「菩薩」との称を付し、世親菩薩・無着菩薩と敬称します。
この書は、説一切有部だけでなく大乗の人々から非常に珍重されるにいたり、大乗の基礎学として必須の書として古来、インドからチベット、モンゴル、支那、そして日本において熱心に学ばれ、研究されていました。
日本では、奈良期から鎌倉期にかけて、これを特に学問・研究する倶舎宗という宗派、というより学派すら存在していました。これは独立の宗派というのでなく、興福寺や薬師寺などを拠点として大いに栄えた、法相宗[ほっそうしゅう]という唯識を宗義とする宗派に付属するものでした。
唯識を理解するには、倶舎を基礎額として学ばないわけにはいきません。
しかし、倶舎の所説を完全に理解するには、宗義とする唯識を学ぶよりも時間がかかることから、「唯識三年 倶舎八年」などと「桃栗三年 柿八年」にかけて言い習わされています。いや、唯識を学ぶのだけではなく、三論宗など中観を理解するにも、天台(法華)・華厳・密教を理解するにも、倶舎を学ぶことは必要不可欠です。
現在もなお、なんであれ声聞乗・小乗だけではなく、どのような宗派であれ大乗を志す者は誰であれ、必ずこの書に触れないわけにはいかないものです。それは今も、チベット仏教の伝統では確かに実行されています。
しかし、現在の日本仏教界では、大変遺憾なことに、これを学ぶ人もその術もほとんど失われているような状況です。
説一切有部における「無我」の理解 ―人空法有
さて、仏教では、諸行無常・諸法無我・涅槃寂静・一切皆苦という四つの句を、仏教の仏教たる所以、その教えの核・世界観の要を表す言葉として用いてきました。
この世の一切は「無常」であり、ならば、その故に我々の経験する全ては畢竟「苦」である。であるならば、我々が我・我が物と思っている諸々のモノはどこまでも不如意なる「無我」であって、実際それは真であると。しかし、それらを全く真であると知り抜いて、それに則った生活を送った時には、そこに涅槃という、一切の心的苦しみから離れた平安なる境地がある。その時には、人は再び生まれ変わって苦を受けることがない、という言葉です。
説一切有部では、我々が経験する常識的な存在、個別の人や事物・事象は仮のものであって実在しない、我いわゆる霊魂のような「不滅の私」・「永遠なる個我」(ātman)なるものなども存在しない、故に無我(anātman)である、と無我を理解。
しかしながら、部派仏教といわれる諸部派がその他なんらかの実在を認めていたように、大きくは二つ、あるいは五つの範疇に分類されるモノが真に実在する、という見解を立て、そのような理解に従った教学を構築しています。
巷間には開口一番「すべては虚妄である。所詮それは、名(ナーマ)と色(ルーパ)にすぎないのであるから」だとか「すべては無自性空である。あれも空だ、これも空だ」などと宣う愚か者があります。
が、説一切有部では、世間で認められる常識的な存在を無碍に否定などしておらず、これを世俗諦(世間的レベルでの真実)とし、対して究極的に認められる存在を勝義諦[しょうぎたい](真に存在するモノ)としています。吾人の知覚し、経験する諸々の事象を、端から否定するような態度は取らないのです。
真実(諦/satya)について、その見方によって二つの階層を設定し、そのそれぞれの価値を認めているのです。そして、そのような真実についての理解の仕方は、その内容とするものこそ相違があるものの、大乗にも引き継がれています。
| - | 意味 | ||
|---|---|---|---|
| 真実 (satya) |
世俗諦 (saṃvṛti- satya) |
世俗有 (saṃvṛti-sat) |
分解し得るもの。壊れ得るもの。世間において有ると承認されるもの。 |
| 勝義諦 (paramārtha- satya) |
勝義有 (paramārtha-sat) |
変わらないもの。自性あるもの。 | |
個我は実在しない。けれども、生命・事物など仮の現象を構成する、真に実在するモノがあるという見解を、大乗では「人空法有[にんくうほうう]」などと云います。
そして、そのような見解自体、またそのような見解を至高として奉持する人々は、同じ仏教であっても、大乗の立場から小乗(Hīnayāna)すなわち「不完全な教え」・「劣った教え」と見なされてきました。特に説一切有部は、インドで最大勢力を誇る部派の一つであったこともあり、その見解・学説は、大乗の主要な批判対象となっています。
三世実有 法体恒有
説一切有部の見解で特筆すべきは、それら一切は、現在の瞬間瞬間すなわち刹那において生・住・異・滅と生滅変化しているけれども、過去・未来・現在にわたって実在する、としている点です。
そのような見解を古来、「三世実有 法体恒有」と称します。説一切有部の宗義における一大眼目です。
しかし、説一切有部から直接に分立したとされる経量部などは「現在有体 過去無体」、すなわち現在の瞬間には実在するけれども過去においては実在しないとしており、また他の部派においても見解を大いに異にしています。『倶舎論』の中で世親菩薩は、自身が説一切有部に属していながらも、有部の宗義の眼目であるこの点を大いに批判。経量部の立場から三世に実在などせず、現在においてのみ法は実有であるとしています。
さて、では説一切有部の見た三世に渡って実在する「全てのモノ」、真に実在するモノとはなんであったか。これを簡潔に表にして示せば、以下のようなものです。
| - | 名目 | 意味 | 法数 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 一切法 (sarva- dharmā) 【75】 |
有為 (saṃskṛta) 【72】 |
生・住・異・滅と変化し、転変するもの。言葉に依拠するもの。 | |||
| 色 (rūpa) |
もの。物質の本質。物を成立させている構成要素。 | 11 | |||
| 心 (citta) |
こころ。精神活動の主体となるもの。心王[しんのう]などとも。 | 1 | |||
| 心相応行 (citta-prayukta saṃskāra) |
こころの働き。こころと伴って働くもの。心所[しんじょ]、あるいは心数[しんじゅ]とも言う。 | 46 | |||
| 心不相応行 (citta-viprayukta saṃskāra) |
心と相応することなく、また色とも性質を異にするもの。行蘊・法界に摂せられる。 | 14 | |||
| 無為 (asaṃskṛta) 【3】 |
生・住・異・滅と変化・転変すること無いもの。 | ||||
| 虚空無為 (ākāśa) |
空間。物質が存在することを遮ることのないもの。 | 1 | |||
| 択滅無為 (prati- saṅkhyā- nirodha) |
涅槃。慧によって煩悩の束縛を離れて得られるもの。絶対の平安。 | 1 | |||
| 非択滅無為 (aprati- saṅkhyā- nirodha) |
その条件を欠いている為に、現象することが決して無いもの。 | 1 | |||
これら一切法は、五の範疇に総じては七十五の法が数えられることから、「五位七十五法」と言い習わされています。
これら列挙される法は、すべて真に実在するモノであり、逆にこれら以外の実在を説くのは誤りである、というのが説一切有部における見解です。
もっとも、説一切有部自体が、一切法を「七十五」という数で確定して見ていたというわけでは、実はありません。この点、現在の日本の仏教者の中には、大いに誤解している人が多くあると思われます。
そもそも『倶舎論』では、それを数え上げてみたならば、ただ七十一法が確定的に説かれているのみで、その全体数に言及しているものではありません。もっとも、五位というのは、『倶舎論』はもとよりその他の説一切有部の論書にも説かれている五つの範疇のことであって、これは説一切有部以来のものです。
しかし、唐代の支那において玄奘三蔵門下の普光によって著されて以来、相当なる権威をもって用いられている優れた注釈書『倶舎論記』三十巻(一般に『光記』と略称される)において四つが確定され、ついに七十五法となって以来そのように言い習わされるようになったものです。
これは支那以来の、しかも大乗の宗で言われ出したことであって、インド以来のものではありません。
ただ、それは無論、その理あって為されたことで無根拠なものなどでは決してありません。が、このことは一応知っておくべきものではあるでしょう。なお、その曖昧な記述があるのは、いまから問題とする心所のうち、不定地法についての箇所です。
2.説一切有部の心所説一覧表
『倶舎論』の心所説
ここでは特に、先に挙げた一切法のうち、有為法に属してその数四十六法が数えられる、心相応行すなわち心所に焦点を当て、これを表にして列挙したものを以下に示します。
ここで依用したのは玄奘三蔵訳『阿毘達磨倶舎論』で、まず一々玄奘三蔵による漢訳語を挙げています。しかしまた参考までに、サンスクリット原本も参照し、併せて括弧内にそのサンスクリット原語を併記しています。
さらに併せて、それぞれ心所の作用、意味内容をも簡潔に記しています。これは『倶舎論』本文ならびにその注釈書、普光『倶舎論記』ならびに法寶『倶舎論疏』を参照して記したものです。
(如何せん、不肖愚鈍の私の為したもののことですから、つまらないミスや不適切であったり妥当でないものがある可能性があります。)
これら心所の一々の名目は、旧訳・新訳の間で訳語が大きく異なっていることこそありますが、原則として経典にある言葉であるために他部派とほとんど共通するものです。しかし、時として部派によってその心所の定義などが異なり、意味内容が相違しています。故に語句が同じであるからといって、必ずしも他の部派と同じ意味内容のものでないことを注意しなければなりません。
| - | 品名 | 品名の由来・意味 | |
|---|---|---|---|
| 名目 | 作用・意味 | ||
| 心所 (caitasika) 【46】 |
大地法 (mahā- bhūmika) 【10】 |
すべての心の生じるあらゆる場所・瞬間に、遍く従って倶に起こる心の作用。大地の大は遍きこと、地は拠り所たる心王を意味し、すべての心王に伴って起こるから大地法という。 (*以下に列挙する順に次第して働くとされるわけではない) |
|
| 受 [じゅ] (vedanā) |
感受・感覚。身体的苦・楽・不苦不楽、精神的喜・憂・捨いずれかを感じる働き。 | ||
| 想 [そう] (saṃjñā) |
表象・知覚。感覚した対象の、例えば男女など、その差異を知る働き(取相)。 | ||
| 思 [し] (cetanā) |
意思。考える働き。行蘊のうち最も勢力ある、心の主たる働き(造作)。 | ||
| 触 [そく] (sparśa) |
刺激。感覚器官(根)と対象(境)と認識(識)とが相応して生じる働き(触対)。 | ||
| 欲 [よく] (chanda)* |
意欲・欲求。身口意いずれかで、何らか行為せんとする動機となる働き(希求)。 | ||
| 慧 [え] (mati)* |
判断。物事の是非などを選択する働き(簡択)。 | ||
| 念 [ねん] (smṛti)* |
記憶。認識している対象を明らかにして忘れず留める働き(不忘)。 | ||
| 作意 [さい] (manaskāra) |
喚起。気づき。心を覚醒、或は揺動させ、感覚する対象に引きつける働き(驚覚)。 | ||
| 勝解 [しょうげ] (adhimokṣa)* |
確認。知覚する対象を、それが何であって、何でないことはない、と確定する働き(印可)。 | ||
| 三摩地 [さんまぢ] (samādhi)* |
集中。定めた認識対象から意識をそらさない働き(心一境性)。 | ||
| 大善地法 (kuśala- mahā- bhūmika) 【10】 |
善なる心の生じるあらゆる場所・瞬間に、遍く従って倶に起こる心の作用。すべての善心に伴って起こるから大善地法という。 | ||
| 信 [しん] (śraddhā) |
心を澄浄とする働き。真実を目の当たりにして確信する働き(信澄浄)。 | ||
| 不放逸 [ふほういつ] (apramāda) |
諸々の善をなすことに専注させる働き。放逸の対。 | ||
| 軽安 [きょうあん] (praśrabdhi) |
安心。心身をして軽快・爽快とする働き。 | ||
| 捨 [しゃ] (upekṣā) |
平等。心をして何事にも動じさせない働き。 | ||
| 慚 [ざん] (hrī) |
敬すべき人・物事を敬重する働き。或は、自らの罪について自ずから恥じる働き。 | ||
| 愧 [き] (apatrapā) |
罪を犯す事に怖れを生じる働き。或は、自らの罪について他者に対して恥じる働き。 | ||
| 無貪 [むとん] (alobha) |
無執着。感覚する対象に欲心を起こし、執着しようとしない働き。 | ||
| 無瞋 [むしん] (adveṣa) |
対象の生物・無生物問わず、怒りを起こさない働き(慈)。 | ||
| 不害 [ふがい] (maññati) |
他を損害しようと欲することのない働き(悲)。 | ||
| 勤 [ごん] (vīrya) |
心を勇ませて悪に対抗させる働き。懈怠の対。 | ||
| 大煩悩地法 (kleśa- mahā- bhūmika) 【6】 | どのような煩悩であれ、それが心に生じるあらゆる場所・瞬間に、遍く従って倶に起こる心の作用。煩悩に染せられたすべての心に伴って起こるから大煩悩地法という。 | ||
| 痴 [ち] (moha) |
愚痴。真実をわきまえず理解しない働き。全ての煩悩の拠り所(無明)。 | ||
| 放逸 [ほういつ] (pramāda) |
心を散漫にして、諸々の善をなさない働き。不放逸の対。 | ||
| 懈怠 [けたい] (kauśīdya) |
心を怠らせ、むしろ悪をなすに勇ませる働き。勤の対。 | ||
| 不信 [ふしん] (āśraddhya) |
心を曇り濁らせ、澄浄としない働き。信の対。 | ||
| 惛沈 [こんぢん] (styāna) |
鬱。心身をして鈍重に、塞ぎ込ませる働き。 | ||
| 掉挙 [じょうこ] (auddhatya) |
躁。心をして騒がしく、落ち着かせない働き。 | ||
| 大不善地法 (akuśala- mahā- bhūmika) 【2】 |
不善なる心の生じるあらゆる場所・瞬間に、遍く従って倶に起こる心の作用。すべての不善心に伴って起こるから大不善地法という。 | ||
| 無慚 [むざん] (āhrīkya) |
敬すべき人・物事を敬重しない働き。或は、自らの罪について自ら恥じぬ働き。 | ||
| 無愧 [むき] (anapatrāpya) |
罪を犯す事を恐れない働き。或は、自らの罪について他者に対して恥じない働き。 | ||
| 小煩悩地法 (parītta- kleśa- bhūmika) 【10】 |
ある場所・瞬間の心に、無明以外のその他の煩悩とは倶なることなく生じる心の作用。限定された小分の煩悩に染せられた心に伴って起こるから小煩悩地法という。 | ||
| 忿 [ふん] (krodha) |
忿怒。己の意思に適わない対象、思い通りにならない人・物事に憤る働き。 | ||
| 覆 [ふく] (mrakṣa) |
隠蔽。己のなした罪過・悪事を隠そうとする働き。 | ||
| 慳 [けん] (mātsarya) |
吝嗇。己の保持する財産、法(教え・情報)を物惜して、他に施そうとしない働き。 | ||
| 嫉 [しつ] (īrṣyā) |
嫉妬。他の成功・優勢・徳性・長所について喜びを起こさず、不快とする働き。 | ||
| 悩 [のう] (pradāsa) |
それが悪であることを知りつつ、または他からの諫言も容れず、執着して悪事を行なって、むしろ自ら懊悩する働き。 | ||
| 害 [がい] (vihṃisā) |
害意、敵意。怒りの対象に危害を加えようとする働き。 | ||
| 恨 [こん] (upanāha) |
怨恨。怒りの対象を、いつまでも思い起こして、捨てることのない働き。 | ||
| 諂 [てん] (māyā) |
己の内心を隠し取り繕って、他を偽ろうとする働き(心曲)。 | ||
| 誑 [おう] (śāṭhya) |
詐欺。己の実際の徳・品性などを粉飾して、他を欺こうとする働き。 | ||
| 憍 [きょう] (mada) |
己の才覚・財産・地位などに愛着し、自らおごり高ぶる働き。 | ||
| 不定地法 (aniyata) 【8】 |
ある時は善心、ある時は煩悩に染まった染心、またある時はそのいずれでもない無記心において生じる心の作用。いずれかに定まった心に起こるものでないから不定地法という。 | ||
| 悪作 [あくさ] (kaukṛtya) |
己の過去に為した、又は為さなかった善・悪の行為を追憶して、それを後悔する働き。 | ||
| 睡眠 [すいめん] (middha) |
心を惚けさせ、不明瞭・不活発にさせる働き(昧略)。 | ||
| 尋 [じん] (vitarka) |
思考。知覚する対象について、漠然と考える働き。粗雑な識の働き。 | ||
| 伺 [し] (vicāra) |
思惟・思索。知覚する対象について、細かに考える働き。微細な識の働き。 | ||
| 貪 [とん] (rāga)** |
欲望。己の望みに適う人・物事を欲してやまない、衝動的働き(愛)。 | ||
| 瞋 [しん] (pratigha)** |
怒り。忿ならびに害を除く、自・他の人・物事に対して怒る、衝動的働き(恚)。 | ||
| 慢 [まん] (māna)** |
傲慢。己の才覚・徳・財産・地位などを誇り、他に対しておごり高ぶる働き。 | ||
| 疑 [ぎ] (vicikitsā)** |
疑惑。因縁生起・業果・輪廻を信じることの出来ない働き。 | ||
これら説一切有部の心所説は、説一切有部の阿毘達磨を学習する者、あるいは大乗を学習する者であっても、まず必ず全て記憶して置かなければならないものです。
それを難しいとか多すぎてとても無理などと、それに取り掛かる前から不平を言う人が多くあります。が、たとえば生活・収入に直接関しない娯楽のこと、たとえば映画や歌、本のタイトル、俳優や歌手、著者の名前などかなり多く記憶することが当たり前に出来ている者であれば、誰でも出来ることです。本当に興味があり、これを知りたいという欲求があるならば、それほど困難なことではないと思われますが、どうでしょうか。
といって、実際のところ、最初はこのような漢字の言い回し、漢字一文字だけの術語などに慣れるのに一苦労となるかも知れませんけれども。しかし、やってみれば案外大して難しいことでないことに気づくことでしょう。
注記
上記の表に示したように、説一切有部では大地法に十心所を数え、これを『倶舎論』において世親菩薩も伝えている。けれども世親菩薩はこれについて「伝説である」として異議を唱えている。菩薩の見解は、大乗に転向して後に著された諸論書において知られる。
そこでは、上記表中のサンスクリットの横に*を付した諸々の心所が、一切心に遍く生じるものとはされず「別境」として挙げられている。この点については、分別説部の心所説と似通っている。
不定地法の最後の四つ、サンスクリットの横に**が付されているのは、『光記』において確定された心所。『倶舎論』自体では「等」と略されており、『倶舎論』ではこれらは不定法のうちにははっきりと説かれていないもの。
小比丘覺應(慧照) 拝識
(By Araññaka bhikkhu Ñāṇajoti)
分別説部の心所説 | 説一切有部の心所説 | 瑜伽行唯識の心所説
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。



