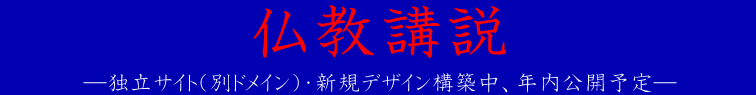
現在の位置
‡ 『四分律』とは
- 目次
- 1.『四分律』
- 2.『四分律』を伝えた部派
- 3.『四分律』翻訳当時の状況
- 4.『四分律』の翻訳者
- 5.漢訳『四分律』
- 6.『四分律』の普及と律宗の誕生
- ← “戒律講説”へ戻る
- ← “著作権について”
1. 『四分律』
『四分律』とは
『四分律[しぶんりつ]』とは、インドから中国に伝わって漢訳された5つの律蔵のうちの一つで、中国はもとより日本においてもっとも実行されてきた、僧侶についての規定や禁止条項などについてが説かれた聖典です。
『四分律』の「四分」とは、その全体が四つに分割され、伝えられてきたことから名づけられたものです。
原典は、分量的に四等分であったかもしれません。しかし、漢語に翻訳され、その分量が60巻にも及んでいる漢訳『四分律』では、初分21巻・第二分16巻・第三分12巻・第四分11巻と、まったく等分とはなっていません。
また、『四分律』を読んでみると、その分割の仕方は、内容によったものではないことが知られます。もっとも、翻訳当初は40巻であったようで、一巻の分量が長大であったためか、後に調巻し直されて今の60巻となったと伝えられています。
『四分律』を伝えた言葉
『四分律』は、いかなる言語によって伝えられたのか。
『四分律』をもたらし、翻訳した僧の伝記を伝える文献では、その言語は胡語であったと伝えています。胡語とは、中央アジアもしくはインドの言葉というおおざっぱな意味から、サンスクリット以外のそれら地域の言語を意味する言葉です。よって、この記述だけでは、よくわかりません。
しかし、おそらく『四分律』はサンスクリットで中国に伝えられたのではなく、スリランカに伝わった上座部の聖典語として伝わる、パーリ語に近いプラークリットによって伝えられたであろうことが推測されます。なぜなら、漢訳された『四分律』にある音写語の多くが、サンスクリットよりもパーリ語により近い言葉を予想させるものが大変多いためです。よって、この胡語の意味は、サンスクリットでは無いインドあるいは中央アジアの言語という意味を示したものと考えても良いでしょう。
ちなみに、サンスクリット(Sanskrit)とは、「正しく造られた(もの)」を意味する言葉で、文法や発音などがきわめて厳密に規定されている、大変洗練された古代インドより伝わる言語です。サンスクリットは、梵天というインドでも最も強力な神の一人とされる神が造った言葉と伝説されており、ゆえに聖なる言語として今なお用いられています。
もっとも、サンスクリットといっても時代によって若干異なっており、現在は三層に分類されています。その中でも最も古い層のサンスクリット、これは紀元前15から10世紀ほどの昔から使用されていたものと推測されていますが、現在Vedic[ヴェーディック]と学問的一般的に呼称されています。しかし、現在にまで伝わり、学ばれているサンスクリットは、Pāṇini[パーニニ]という紀元前4世紀頃のインドの文法学者が文法的に完成させたもので、これをClassical Sanskrit[クラシカル サンスクリット]などと学問の分野では呼称しています。これは、2400年の時を経た現在にても、文法がまったく変わらず伝えられているという極めて珍しい言葉です。
対して、プラークリット(Prākrit)とは、地方によって異なり、ゆえに多数存在した中期インドにおけるサンスクリット以外の俗語の総称です。サンスクリットのように文法が完璧に規定されている洗練された言語ではなく、より簡略で文法に揺れがあり、訛りや癖のある土俗の言語です。パーリ(Pāli)語もそのプラークリットの一つで、西インドの海岸地方にて使用されていた言語、Piśāca[ピシャーチャ]あるいはPisāca[ピサーチャ]語(鬼神語)に起源する言葉と言われています。
南・東南アジアに伝わった上座部では、このパーリ語によってその聖典を伝えています。これは、西インドの海岸地方出身の人(アショーカ王の子息。一説には弟)によって、仏教がインドからスリランカにもたらされた事に由来するのでしょう。
北方に伝わった仏教では、サンスクリットこそ釈尊が使用されていた言語であると伝えるのに対し、南方に伝わる仏教では、パーリ語こそが釈尊が使用されていた言葉である、との伝説を伝えています。が、言語学的には、どちらも釈尊が使用していたというマガダ語とは異なる事が、ほとんど確定しています。しかし、いずれにせよ、同じく中期インド・アーリア語の範疇にある言語であり、互いに相当に似通った、共通点を多く持つ言語で、それほどたいした違いはそこにありません。
故に、それぞれがサンスクリットあるいはパーリ語が釈尊の言葉であった、と伝承していても別に問題の無いことと言え、現在ならば、その両方の言語に通じたならば実に結構、というだけの話だとも言えます。
2.『四分律』を伝えた部派
法蔵部
『四分律』を所依の律蔵として伝持していたのは、上座部から派生した法蔵部です。この部派は、サンスクリットでDharmaguptaka[ダルマグプタカ]あるいはパーリ語でDhammaguttika[ダンマグッティカ]」というため、漢訳経典ではこれを音写した、曇無徳部[どんむとくぶ]の名で呼ばれることもあります。
法蔵とは、この部派が成立したとき最長老であった比丘(すなわち主導者)の漢訳名です。彼は、Aśoka[アショーカ]王の王師であったという、Upagupta[ウパグプタ](漢語音写名は憂婆麹多[うばきくた])尊者の弟子であったと伝えられています。また、法蔵部は、目蓮尊者の法系を引くものであると自称していたことが、説一切有部が伝える部派分裂史『異部宗輪論』(異訳『部執異論』)に伝えられています。
(部派についての詳細は、”枝末分裂-部派仏教-”を参照のこと。)
さらに余談ながら、上座部においては、アショーカ王の王師はウパグプタ尊者ではなく、Moggaliputta Tissa[モッガリプッタ ティッサ](目犍連子帝須)尊者であったとしています。、また両者の生涯に関する伝承に共通点が多いこともあり、両者は同一人物であったとする説を言う人が現在あります。
ウパグプタ尊者は、上座部においては教学上全く知られていない人なのですが、なぜか東南アジアの上座部仏教国にて、ウパグプタ尊者を誰ともわからずに、いや、過去の上座部における強力な神通力ある大阿羅漢の一人であったとして尊崇する習慣が残っています。それらの国では、たとえばビルマでは、彼を南海の島から来た聖人としても捉えています。
ビルマにおいてその像は、胡座した上に鉄鉢を抱え、天を仰ぎ見る姿で統一されています。南海の聖者ということからでしょう、尊者の像は、寺院の池の中央など水に関係する場に祀られている場合が多く見られます。しかし、この姿は、福徳豊かで何処へ行っても衣食に困ることが無かった阿羅漢と言われ、故に富(多くの布施)を求める比丘などから信仰を集めているシーワリ尊者のスリランカにおけるそれと(空を見上げていないだけで)ほとんど同じです。どこかで伝承の混乱が起こったのかも知れません。
沙弥などが試験を前に尊者に祈れば、智慧を授けてくれるなどという信仰が、ビルマと国境を接するインドはアッサム地方周辺にて見られます。
法蔵部の聖典
ちなみに、法蔵部の律蔵は上記のように『四分律』であり、これはもちろん伝わっているのですが、その経蔵については、ただ『長阿含経』のみが漢訳され伝わっているだけで、法蔵部が伝持していた他の阿含経は伝わっていません。論蔵にいたっては、確かに法蔵部のものと言えるものは、『舎利弗阿毘曇論』以外に伝わっていないようです。
また、伝承に依れば、法蔵部は、経蔵・律蔵・論蔵のいわゆる三蔵以外に「陀羅尼蔵」と「菩薩蔵」という聖典群を含めた、いわば五蔵を伝持していたようです。例えばこのことは、慈恩大師基による『異部宗輪論述記』という書にも説かれています。そこには「説総有五蔵一経二律三阿毗達磨四咒即明諸咒等五菩薩即明菩薩本行事等」とあり、この部派が経律論の三蔵に加え(というよりも三蔵から別出し、あるいは蔵外に伝わっていたものを五蔵としてまとめた?)、諸々の明咒を収めた呪蔵と、菩薩本行事すなわち本生譚(ジャータカ)を収めた菩薩蔵を伝持したようです。しかし、それが具体的に例えば現存する経典でいえばいずれを含めたものであるかは、現時点でまるでわかっていません。
現在伝わっているその他の阿含経、『雑阿含経』や『中阿含経』、『増一阿含経』は、説一切有部[せついっさいうぶ]などその他の部派が伝持していた経蔵の一部とされていますが、資料が乏しいため、詳しくはわかっていないのが現状です。
漢訳四阿含
『長阿含経』・『中阿含経』・『雑阿含経』・『増一阿含経』という四つの「阿含」の名を冠する経を、まとめて漢訳四阿含などと呼ぶことがあります。
その昔、中国においても、それぞれの阿含経がどの部派に属しているかに諸説ありました。まず玄奘三蔵の弟子であった慈恩大師(基法師)は、四阿含すべては大衆部のものと見ていました(『法華玄賛』)。また『倶舎論稽古』を著した法幢[ほうどう]は、その中で、『中阿含経』と『雑阿含経』は説一切有部、『増一阿含経』は大衆部、『長阿含経』は化地部、『別訳雑阿含経』は飲光部に属するものと見ています。
いずれにせよ、それら四つの阿含経典群は、一つの部派からそっくりそのままもたらされて漢訳されたものではなく、相異なる部派の経蔵が断片的にもたらされたものです。そして、そのこと自体が、中国においてもよく理解されていなかったことが知られます。
諸部派の伝持した三蔵で、中国にもたらされ漢訳されたものの中で、完全ではないにしろ最もまとまって伝わっているのは、説一切有部のものです。経蔵については先に述べたように部分的なもののようですが、律蔵と論蔵については完全に伝わっています。わずかながらサンスクリット原典も残っています。
もっとも、相異なる部派が伝持してきた経典群であるとは言っても、サンガが伝持してきた仏典であることには変わりませんので、仏典としての価値に優劣をつけることはできません。ただし、伝持してきた部派が違うため、同じ阿含経であるといっても、それぞれの伝承に基づく、思想的見解の相違などが若干見られる場合があるので、そこは注意して読まなければならないこともあるでしょう。
ちなみに、狭義での三蔵が完備して現在まで伝わっているのは、分別説部がパーリ語によって伝承してきた、いわゆる「パーリ三蔵」だけです。
3.『四分律』翻訳当時の状況
律蔵の中国への伝来
さて、『四分律』が漢訳されたのは、中国暦の弘治十二年(410)から同十四年(412)のことです。そして、『四分律』の序文によれば、その翻訳者はインド・カシミール出身の仏陀耶舎[ぶっだやしゃ]尊者と支那人の竺仏念[じくぶつねん]尊者です。
ところで、中国には、律蔵の規定に則った受戒法が、魏の嘉平年間(249-253)にインド僧の曇柯迦羅[どんかから]尊者によって、洛陽にもたらされていました。しかし、それは受戒法がもたらされたというだけで、肝心な律蔵の翻訳は、その約150年後の弘治十一年(409)、『十誦律[じゅうじゅりつ]』という説一切有部の律蔵がもたらされて初めてなされています。
とは言っても、律宗の伝承に依るならば、曇柯迦羅尊者のもたらした戒法は『四分律』によるものだったといいますから、『十誦律』の翻訳がなされたといっても、受戒法とその根拠となる律蔵が不一致となりますので、それではまったく不十分と言えるものでした。
また、曇柯迦羅尊者が中国で訳したのは、『四分律』のそれではなく、大衆部[だいしゅぶ]の波羅提木叉[はらだいもくしゃ]である『僧祗律戒本[そうぎりつかいほん]』であったことが現在知られています。よって、この律宗の伝承は信用しがたいものです。いずれにせよ、それまでの中国では律に対する理解も、その導入も遅れていたのです。
経典・論書に遅れて伝来した律蔵
『四分律』が翻訳された当時の中国は、ようやく律蔵の翻訳がなされたばかりの頃であって、その知識も理解もいまだ不十分な時代です。そして、それは仏教の中国公伝の年であるという永平十年(67)より、すでに四世紀を経ようかとしていた時のことです。
それまで中国に伝わっていた仏教は、経典と論書が部分的に先行して伝わっているだけで、律蔵がまったく欠けているという、本来の仏教からすれば、まったく不完全なものであったのです。
4.『四分律』の翻訳者
仏陀耶舎
そのような時代のなか、時の皇帝、後秦の姚興[ようこう]は、仏陀耶舎というインド・カシミール出身の大変優れた僧侶が、『四分律』という律蔵を携えて長安に入った、という話を耳にします。
そこで姚興は、洛陽・長安をふくむ州の長官たる司隷校尉[しれいこうい]の姚爽[ようそう]に対し、すぐさま仏陀耶舎尊者を招いてその翻訳を要請するよう命を下します。この裏には、数々の大乗経典を壮麗なる美文で訳した三蔵法師として、今なお日本においても讃えられている、Kumārajīva[クマーラジーヴァ](鳩摩羅什[くまらじゅう])の助言があったようです。彼は、以前異国で仏陀耶舎尊者に会い、その教えを受けたことがあって、その広学さと聡明さに感服し、尊敬し続けていたのです。
ところが、仏陀耶舎尊者は『四分律』を異国語で全て暗誦しているのであって、『四分律』が書かれた本を持っているのではありませんでした。
強記の英才
これを知った人々は当初、仏陀耶舎尊者が長大な律蔵を正確に暗記している筈がないと信用しなかったそうです。ですが、試しに中国の書物を暗記させてみたところ、尊者はそれを一語として誤ることなく完璧に暗誦したといいます。
これで晴れて彼が大変な記憶力の持ち主であり、その記憶力が確かなることがわかったので、その疑いを解き、ついに『四分律』の翻訳が開始されたのでした。そして、『四分律』の翻訳を二年間かけて終えた尊者は、引き続き『長阿含経』の翻訳にあたっています。
自戒自律の日々
仏陀耶舎尊者は、訳経している間も、托鉢によって得た食事だけを摂るなど、律に厳格に則った生活を送っていました。この態度は、都で皇帝から半強制的とはいえ女性をあてがわれ、僧侶としては全く失格の、享楽的な堕落した生活を送っていた鳩摩羅什とは対照的なものでした。
ようやく翻訳を終えた尊者に対し、姚興は絹の反物など多くの財物を与えようとしますが、仏陀耶舎はこれら一切を受け取りを拒否し、中国からひっそりと姿を消します。尊者はその後、『虚空蔵経』という経典をカシミールから中国に送っていますが、その最後はどのようなものであったか知る人はいません。
5.漢訳『四分律』
漢訳のみ今に伝わる
さて、そのような経緯を経て翻訳された『四分律』は、それ以降も「書き記されたもの」としてインドまたは中央アジア周辺から伝わることはなかったようです。
梵本またはその他言語の本が中国に伝わって再翻訳されたとの記録はなく、現在も中国はもとよりインドまたはその周辺地域において発見もされていません。また、チベット語訳もされておらず、よって漢訳のみが伝わっています。
重要な事項は記憶
もっとも、仏陀耶舎尊者がそうしていたように、インド文化圏における「もっとも重要なものは書き残さず、完全に記憶し、また口伝えでのみ伝える」という伝統を考えますと、「書き記されたもの」としての律蔵など、最初から無かったようにも思えます。
現代でも、律蔵をまるごと記憶してしまえた者があった、記憶することによって正確に伝えた、などと聞くと、そんな馬鹿な、と思う人が多いかもしれません。しかし、この、インド文化圏における膨大な分量の文言をそのまま記憶して伝えるという伝統は、いまだチベットやビルマ、スリランカなど周辺国にて保存されています。実際、今もインド文化圏における伝統的学習法は、まず丸暗記することか始まります。
それらの国々では、実際に信じられない量の文献を、完全に記憶している者が少なくありません。ビルマには、パーリ語の三蔵全部を完全に記憶している僧が、現在でも5人以上存在しています。インド本国にて仏教は滅びたものの、しかしヒンドゥー教のごく一部のバラモンは、やはり膨大な量のヴェーダを丸暗記しており、それはむしろ義務であると言います。
いや、そもそも世界的に見ても、古典などを学ぶにあたって、まず学生に課せられるのはその暗記暗誦であり、それが出来て初めて意味が解説されることを思えば、尊者が律蔵を丸暗記して伝えたことについては、それほど驚くべきことでもないかもしれません。
現在『四分律』を収録している典籍
現在、この『四分律』は『大正新修大蔵経』22巻の567~1014項に収録され、『国訳一切経』律部1~4には、その全文の読み下し文と若干の註記が付されて載っています。
なお、上に挙げた仏陀耶舎尊者の伝記は、『出三蔵記集』(『大正新修大蔵経』55巻,P20中段)ならびに『梁高僧伝』(『大正新修大蔵経』50巻,P333下段)に記されています。
6.『四分律』の普及と律宗の誕生
四分律宗の誕生
さて、中国では当初、最初に伝来し翻訳された説一切有部の律蔵である『十誦律』が盛んに研究され、さらに『四分律』が上に見てきたように翻訳されます。そして、いわゆる「四律五論」などと言われるように、『五分律[ごぶんりつ]』や『摩訶僧祗律[まかそうぎりつ]』などの律蔵も次々と漢訳され、学ばれ始めました。
当初、『十誦律』がもっぱら研究され、これに基づいた僧侶の行事が実行されていたため、ほとんどかえりみられることのない存在であった『四分律』ですが、しかし、やがてその内容が他の律蔵に比べてよく整っており、理解しやすいと認識されるようになって、『四分律』が律学の主流となるにいたります。
そして、ついには四分律を主に学び行う四分律宗が成立し、この系統から南山大師道宣[どうせん]という高僧が出ます。道宣律師は、『四分律』を大乗の立場から解釈した注釈書類を著し、それが以降、権威あるものとして中国一般にて用いられるようになります。
日本に初めて律を伝えた天台の学僧、鑑真和上は、律の血脈からいうとこの道宣律師の孫弟子にあたりますので、当然のことながらその律は『四分律』に基づくものでした。
日本にもっとも縁のあった律蔵
このようなことから、『四分律』以外の律蔵が研究対象にされることはありましたが、日本に於いて実質的に行われたのは『四分律』のみです。東大寺戒壇院での受戒は、もっぱらこれに依るものでした。
もっとも、江戸期における第二期戒律復興運動の中、高野山などでは真言宗では『四分律』ではなく「根本説一切有部律(以下「有部律」)」をこそ、行うべきとの主張がなされ、一時期実行されています。これは、弘法大師空海がその著『三学録』の中で、真言門徒の学習すべきものとして有部律の典籍を列挙していることを、今更ながらに取りざたしたものです。
しかし、これは真言宗のごく一部だけに見られた主張です。慈雲尊者も、正法律運動の中で「有部律」を研究・参照、その講義も行っていますが、律の実行に際してはほとんど『四分律』に依っています。よって、『四分律』は、中国はもとより日本にもっとも縁の深かった律蔵である、と言うことが出来るのです。
律について三度の盛衰を見た日本
しかし現在、大変残念なことに、この『四分律』の戒律の伝統は明治維新の後衰退し、日本において再び(正確にはこれで三度目ですが)、潰えました。奈良の唐招提寺を本山とする律宗ですら、現在の管長が立宗以来初の妻帯者という有り様で、日本仏教においてサンガは消滅し、本当の意味での仏教僧を生み出す機構・組織はまったく存在しなくなっています。
いま、律宗が具足戒の授戒会を開く時には、自分たちで実行することが不可能であるために、中国の律宗から長老比丘らを招いて開いています。なんとなれば、律宗では、具足戒を受けたか否かを、自宗の僧籍資格の絶対条件としているためです。
しかし、この行為は、極めて滑稽な、ただちに改めたほうが良い愚行です。はじめから妻帯・世襲することを前提として、正式な具足戒を開壇してこれを受けると言うことは、とりもなおさず、わざわざ波羅夷罪を犯すためだけに比丘となるようなものだからです。受けなければただの悪業で済む(?)ものを、わざわざ押して比丘となって極重罪を犯すというのですから、これ以上の滑稽な愚行もないでしょう。
長い伝統を誇り、往事は極めて勝れた僧侶の数々を輩出した律宗というものの現在が、どこまで堕したものであるかを理解するのに、これ以上の好例はありません。近年甍を新たにし、伽藍の威容はいよいよ見事となったのに反して、その中身は、平安後期に戒律復興の先鞭をつけた中川実範[なかのかわ じっぱん]上人が唐招提寺を訪れた時の昔以上に、衰退しきってしまったようです。なんとも残念なことと言わざるを得ません。
日本仏教の歴史を顧みると、300年から400年の周期で戒律復興運動が起っているようです。槙尾山の明忍律師が慶長の世に戒律を復興してからはや400年を過ぎ、慈雲尊者の正法律が唱えられてからは260年が経過しています。しかし、そして、それら復興された戒律の風が止んでから、すでに100年を経過しようとしているとみて良いでしょう。
近い将来、この日本の地に、再び戒律の風を起こして仏教という旗をたなびかせる人が現れることを、望んで止みません。
沙門 覺應 (horakuji@live.jp)
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。




