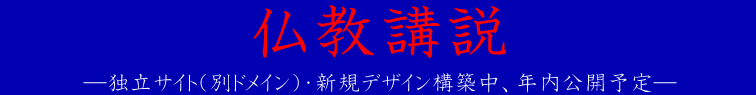
現在の位置
‡ 訶梨跋摩 『成実論』止観品(解題・凡例)
解題・凡例を表示
解題・凡例 |
1 |
2 |
3 |
4 |
原文 |
訓読文 |
現代語訳
![]()
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
1.解題
『成実論』とは
『成実論[じょうじつろん]』は、中インドのバラモン出身の僧、訶梨跋摩[かりばつま](Harivarman[ハリヴァルマン])によって、西暦3-4世紀頃に著された書です。
梵本(サンスクリットあるいはその他インド語による原本)はもとより、チベット語訳も伝わっておらず、ただ鳩摩羅什[くまらじゅう](Kumārajīva[クマーラジーヴァ](344-413)によって訳された、この漢訳本だけが伝わっています。現在、仏教学者などによって、その原名はTattvasiddhi-śāstra[タットヴァシッディ・シャーストラ]あるいはSatyasiddhi-śāstra[サティヤシッディ・シャーストラ](邦語で「真実を成就する論」)ではなかったか、などと推測されています。
鳩摩羅什によって漢訳がなされると、この書は盛んに研究され、成実宗なるこの書を専門に研究する学派まで生まれています。しかし後代、この書が他宗の学僧などから小乗の書で一段低いものであるなどと位置づけられるようになって衰退。複数著された注釈書も今や散失し、現存していません。故に、この書をいま一一理解していくには、多少の困難が伴うことがあります。また本書の内容からして、これを理解するには、まず四阿含の経典に親しみ、他部派の教義、特に説一切有部の典籍にある程度通じていることや、外道論師の諸説など広く知っている必要もあります。
なお、成実宗は、日本にも奈良時代に伝わっています。いわゆる南都六宗の一つ、鎌倉後期の凝然大徳『八宗綱要』にて挙げられた日本の伝統宗派の一つです。もっとも、日本でも成実宗は、三論宗(中観派)の寓宗というべき位置(そもそもが今言われるような「宗」と言うよりもむしろ「学派」あるいは「科目」のようなもの)となり、鎌倉期において完全に消滅しています。
しかしいずれにせよ、宗としては現存していなくとも、『成実論』は、漢語仏教圏において、小乗の諸部派ならびに大乗を学ぶ上で不可欠である書であることは、現代にいたるまで変わりありません。
訶梨跋摩について
著者の訶梨跋摩については、その昔の支那にて伝記があったようですが今は散失して伝わってないため、よくわかっていません。ただ、梁の僧裕『出三蔵記集』(大正55,P78中段)や唐の道宣『広弘明集[こうぐみょうしゅう]』(大正52,P244中段)にて、さらには南宋の法雲『翻訳名義集[ほんやくみょうぎしゅう]』(大正54,P1066上段)には極めて簡潔に、その生涯が若干記されています。
それらで伝えられているところをまとめると、訶梨跋摩は、仏滅後九百年(『広弘明集』では八百年余後)の中インドにて、バラモンの子として生ま,れ、幼少からヴェーダなど世典を学び外教に通じるも、やがて説一切有部の大碩学、達摩沙門 究摩羅陀[くまらだ](Kumāralāta[クマーララータ])の弟子として出家。優れて聡明なることで世に名を馳せ、のちに成実論を著すに至ったようです。これら伝承からは、彼がいずれの部派に属してこの書を著したかは定かではありません。
なお、訶梨跋摩のサンスクリット名がHarivarman[ハリヴァルマン]であろうとほぼ現在断定されているのは、それら伝承にその漢訳名が「師子鎧」であるとされていることによります。
ちなみに、訶梨跋摩の和尚(根本師)であったという究摩羅陀[くまらだ]とは、経量部[きょうりょうぶ]を創始したと言われる人で、その学徳は桁外れに高かったといいます。玄奘三蔵の『大唐西域記』(大正51,P942上段)に依れば、当時(2-3世紀)のインドには、四人の太陽に比すべき大徳があって世を照らしていたと言います。すなわち、東インドの馬鳴[めみょう](Aśvaghoṣa[アシュヴァゴーシャ])、南インドの提婆[だいば](Deva[デーヴァ]/Āryadeva[アーリヤデーヴァ])、西インドの龍猛[りゅうみょう](Nāgārjuna[ナーガールジュナ])、北インドの童受(すなわち究摩羅陀)の四人です。
ここに挙げられた究摩羅陀を除く三人は、後代に与えた影響はすこぶる大きく、今も彼らの優れた著作を目にすることが出来、いまだ偉大な高僧として崇められています。しかし、究摩羅陀の名はごく一部の人が知るのみとなり、彼も当時多くの優れた書を著していたようですが、本書にその詩偈が引用されるのみで、現在はほとんど(漢訳本は全く)伝わっていません。
『成実論』の内容
『成実論』は、ある立場から仏教の根幹・精髄たる四聖諦[ししょうたい]を説き明かした綱要書と言えるものです。
その内容から、小乗十八部派(あるいは二十部)のうち、経量部[きょうりょうぶ]の立場から著されたものであると見られています。経量部は、法の三世実有を説く説一切有部に対し、現在にのみ法の有体を主張して、過去・未来における法の実在を否定したことで知られる部派です。この書の中で訶梨跋摩は多く「空」を説いており、大乗との親和性が古来論じられています。最終的には、支那の大乗の諸学僧によって小乗の教と位置づけられていますが、しかし南山大師道宣などは「分通大乗(大乗に通じる教え)」であると依然評価しています。
この類の書は、現代で言うならば想定問答集と言ったところのもので、決まって問答体で著されると言えるのですが、やはりこの書も同様に全編が問答体にて綴られています(このような形式はインド以来、チベット、支那そして日本に引き継がれます)。
さて、この書ではもやはり同様に、さまざまな立場に立つ仮想問者が登場し、次々と設問あるいは論難を展開。答者(著者)がこれに一々答え、自身の依って立つ見解を明らかにしていきます。議論される内容は実に幅広いもので、それを通して四聖諦を戒・定・慧の三学に開いて説いていかれます。設定される問者として、説一切有部といった仏教の部派だけではなく、外教であるニヤーヤ(正理学派)やサーンキャ(数論派)、ヴァイシェーシカ(勝論派)などのインド哲学派と思われるものも登場しています。
ここで紹介している『成実論』止観品[しかんぼん]は、止観という瞑想法の修め方を斯々然々と説くものではなく、止観とは如何なるものか、その位置づけを(おそらくは)経量部の立場から明らかにしているものです。
伝統的学道、修道の為に
ある一つのことを体系立てて説く書物などの、ある書の単独の章を拾い読みすることは決して良いことではなく、むしろ人をして一知半解の過失に導く恐れが大なるものです。
かく言いながら、愚生の能力・時間ならびに資具不足のため、ここで紹介しているのは『成実論』のうち、ただ止観に焦点をあて論じている止観品のみです。『成実論』は止観に関する瞑想法について他所にて散説しており、より詳しく知ろうと思う者は、当然ながらこの書を通じて、そして幾たびか読む必要があります。
また特にこと止観に関しなくとも、漢語仏教圏において、伝統的道程を踏まえて小乗はもとより大乗を知ろうという者、かたじけなくも仏陀の教えを渉猟してその奥源を見極めんと志す者に、この『成実論』は必読の書の一つです。事実、支那以来、多くの著名な鈔疏にこの論書が引用されています。また、説一切有部の見解を知るにも、またその著名な論書ながら経量部の見解を用いて有部の教学を批判的に概説していると言われる『倶舎論』を理解するにも、経量部のものと思われるこの『成実論』は実に貴重な書となるでしょう。
この拙訳をきっかけとして、日本にも再び『成実論』を学習する者の増えることがあれば幸いです。そしてまた、この書だけではなく、『成実論』を理解するに必要な漢訳四阿含(ならびにパーリ五部)はもとより、『倶舎論』(あるいは『順正理論』)を初めとして『大智度論』など伝統的に重用されてきた仏典を、少しでも再び学習する人の増すことを願うばかりです。
そして、ただ学ぶだけではなく、たとえそれが少数であったとしても、それを我が道として我が足でたゆまず歩む人々の現れることを願ってやみません。
非人沙門覺應 敬識
(horakuji@gmail.com)
![]()
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
2.凡例
本文
このサイトで紹介している『成実論』は、大正新修大蔵経32巻所収のもの(経典番号:1646)を底本とした。
原文は漢文であるが、読解に資するよう、さらに訓読文・現代語訳を併記し、対訳とした。
旧漢字は現行のものに適宜改めている。また、難読と思われる漢字あるいは単語には、ルビを[ ]に閉じて付している。
現代語訳は、基本的に逐語的に訳している。しかし、読解を容易にするため、原文にない語句を挿入した場合が多々ある。それら語句は( )に閉じ、挿入語句であることを示している。しかし、挿入した語句に訳者個人の意図が過剰に働き、読者が原意を外れて読む可能性がある。注意されたい。
語注
語注は、とくに説明が必要であると考えられる仏教用語などに適宜付した。
本文中、仏典などからの引用がなされていた場合は、判明した範囲でその出典を語注にて記した。ただし、あくまで判明している範囲であって、すべてに為されているわけではない。本稿は作業途上のものであるため、逐次判明次第加筆していく。
非人沙門覺應 敬識
(horakuji@gmail.com)
![]()
前の項を見る![]() 次の項を見る
次の項を見る ![]()
解題・凡例を表示
解題・凡例 |
1 |
2 |
3 |
4 |
原文 |
訓読文 |
現代語訳
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。




