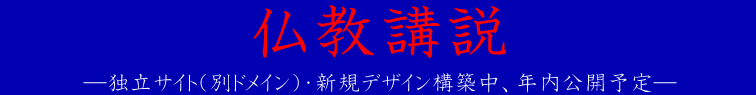
現在の位置
‡ 訶梨跋摩 『成実論』止観品(1)
4ページ中1ページ目を表示
解題・凡例 |
1 |
2 |
3 |
4 |
原文 |
訓読文 |
現代語訳
1.原文
成実論 巻第十五
止観品 第百八十七
訶梨跋摩 造
姚秦三蔵 鳩摩羅什 訳
問曰。佛処処経中告諸比丘。若在阿練若処。若在樹下若在空舍。応念二法。所謂止観。若一切禅定等法皆悉応念。何故但説止観。
答曰。止名定観名慧。一切善法従修生者。此二皆攝。及在散心聞思等慧亦此中攝。以此二事能辦道法。所以者何。止能遮結。観能断滅。止如捉草観如鎌刈。止如掃地観如除糞。止如揩垢観如水洗。止如水浸観如火熟。止如附癰観如刀決。止如起脈観如刺血。止制調心観起沒心。止如灑金観如火炙。止如牽繩観如用剗。止如鑷鑷刺観如剪刀剪髮。止如器鉀観如兵杖。止如平立観如発箭。止如服膩観如投藥。止如調沒観如印印。止如調金観如造器。
又世間衆生皆墮二辺。若苦若楽。止能捨楽観能離苦。又七浄中戒浄心浄名止。餘五名観。八大人覚中六覚名止。二覚名観。四憶処中三憶処名止第四憶処名観。四如意足名止四正勤名観。五根中四根名止慧根名観。力亦如是。七覚分中三覚分名止。三覚分名観。念則俱隨。八道分中三分名戒。二分名止。三分名観。戒亦屬止。
又止能断貪観除無明。如経中説。修止則修心。修心則貪受断。修観則修慧。修慧則無明断。又離貪故心得解脱。離無明故慧得解脱。得二解脱更無餘事故但説二。
2.訓読文
成実論 巻第十五
止観品 第百八十七
訶梨跋摩 造
姚秦三蔵 鳩摩羅什 訳
問て曰く。仏は処処の経の中*1 に諸の比丘*2 に告げていわく、若しは阿蘭若処*3 に在りても、若しは樹下に在りても、若しは空処に在りても、応に二法を念ずべし、所謂止観*4 なりと。若し一切の禅定*5 等の法の皆な悉く応に念ずべくんば、何故に但だ止観を説くのみや。
答て曰く。止を定に名づけ、観を慧に名づく。一切善法の修より生ずるは此の二に皆な摂し、及び散心*6 に在る聞思等の慧*7 も亦た此の中に摂す。此の二事を以て能く道法を辦ず。所以者何[ゆえいかんとなれば]、止は能く結*8 を遮し、観は能く断滅すればなり。止は草を捉うるが如く観は鎌の刈るが如し。止は地を掃うが如く観は糞を除くが如し。止は垢を揩うが如く観は水にて洗うが如し。止は水にて浸すが如く観は火にて熟すが如し。止は癰に附すが如く観は刀にて決するが如し。止は脈を起こすが如く観は刺血するが如し。止は心を制調し、観は没心を起こす。止は金を灑ぐが如く観は火にて炙る如し。止は縄を牽くが如く観は剗を用うるが如し。止は鑷をもって刺を鑷むが如く観は剪刀にて髪を剪るが如し。止は器鉀の如く観は兵杖の如し。止は平立するが如く観は箭を発つが如し。止は膩を服するが如く観が薬を投ずるが如し。止は没*9 を調うるが如く観は印を印するが如し。止が金を調うるが如く観は器を造るが如し。
又た世間の衆生*10 は皆二辺*11 に堕して、若しは苦、若しくは楽なるも、止は能く楽を捨し観は能く苦を離る。又た七浄*12 の中に戒浄と心浄とは止と名づけ、餘の五は観と名づく。八大人覚*13 の中に六覚は止と名づけ、二覚は観と名づく。四憶処*14 の中に三憶処は止と名づけ、第四憶処は観と名づく。四如意足*15 を止と名づけ四正勤*16 を観と名づく。五根*17 の中に四根を止と名づけ慧根を観と名づく。力*18 も亦た是の如し。七覚分*19 の中の三覚分は止と名づけ、三覚分を観と名づく。念は則ち俱に隨う。八道分*20 の中の三分は戒と名づけ、二分は止と名づけ、三分は観と名づく。戒は亦た止に属す。
又た止は能く貪*21 を断じ観は無明*22 を除く。経の中に説くが如し。止を修するは則ち心を修し、心を修するは則ち貪受を断ず。観を修すは則ち慧を修し、慧を修するは則ち無明を断ず。又た貪を離るるが故に心解脱*23 を得、無明を離れるが故に慧解脱*24 を得。二解脱を得れば更に餘事無きが故に但だ二を説くのみ。
3.現代語訳
成実論 巻第十五
止観品 第百八十七
訶梨跋摩 造
姚秦三蔵 鳩摩羅什 訳
問い: 仏陀は様々な経典の中で諸々の比丘達に説かれている。「あるいは森林にあっても、あるいは樹下にあっても、あるいは人気のない処においても、まさに二法を修めなければならない。所謂止と観とである」と。もし一切の禅定などの教えを皆ことごとく修めなければならないものだというならば、何故にただここでは止観とだけ説かれたのであろうか。
答え: 止を定と名づけ、観を慧と名づけるのである。一切の善法を修めることによって生じるものは、この(止と観との)二つにすべて収められるものであり、および散心における聞法と思法との慧もまたこの(止と観との二法の)中に集約される。この二つの方法でもってよく仏道は成じられるのである。その故は、止は能く煩悩を遮り、観は能く断滅するからである。止とは(刈るべき)草を捉えるようなものであり、観は(その捉えた草を)鎌で刈るようなものである。止とは地面を掃くようなものであり、観は(汚れ・臭いの元である)糞を取り除くようなものである。止は垢をぬぐうようなものであり、観はそれを水にて洗い落とすようなものである。止は水に浸すようなものであり、観は火にて熱するようなものである。止は癰[はれもの]に(膏薬を)付けるようなものであり、観は(癰を)刀にてそぎ落とすようなものである。止は脈を強くするようなものであり、観は刺血によって(根治させる)ようなものである。止は心を制し調え、観は没心を起こす。止は(汚れた)金を濯ぎ洗うようなものであり、観は火でもって炙るようなものである。止は縄を引いて(根を起こす)ようなものであり、観は剗[せん]を用いて(地面を平らかにする)ようなものである。止は毛抜きで刺を挟むようなものであり、観は剪刀で髪を切るようなものである。止は甲冑のようなものであり、観は武具のようなものである。止は安定して(狙い)構えるようなものであり、観は矢を放つようなものである。止は(薬用の)膩[あぶら]を服用するなものであり、観は薬を飲むようなものである。止は朱肉を調えるようなものであり、観は印を押すようなものである。止は金属を精錬するようなものであり、観は(その精製した金属でもって)器を作るようなものである。
また、世間の生ける者は皆な二つの極端に陥り、一方は極端な禁欲主義を指向し、他方は極端な享楽主義に奔るが、止は能く極端な享楽主義を捨て、観はよく行き過ぎた苦行主義を離れる。また、七浄の中の戒浄(戒律を厳に持つこと)と心浄(禅定を得ること)とは止に配当され、他の五浄(諸々の邪見を離れること)は観に配当される。八大人覚の中の(小欲・知足・遠離・精進・正憶・定心の)六覚は止に配当され、余の(智慧・無戯論の)二覚は観に配当される。四憶処(=四念処)においては初めの(身念処・受念処・心念処の)三憶処を止に配当し、第四憶処(法念処)は観に配当される。四如意足(=四神足)は止に配当され、四正勤は観に配当される。五根の初めの(信根・精進根・念根・定根の)四根は止に配当され、慧根は観に配当される。これは五力もまた同様である。七覚分(=七覚支)の中の三覚分は止に配当され、他の三覚分は観に配当される。念は止と観との両方を含むものである。八道分(=八正道)の中の三分は戒に配当され、二分は止に配当され、三分は観に配当される。もっとも、戒は(七浄の戒淨を止として挙げたように)止に属するものである。
また、止は能く貪欲を断じ、観は無明を除く。経の中に説かれているとおりである。止を修するのは則ち心を修めることであり、心を修れば則ち貪欲の享受が断じられるのである。観を修するのは則ち慧を修することであり、慧を修めれば則ち無明が断じられる。また貪欲を離れる故に心解脱を得、無明を離れる故に慧解脱を得る。これら二つの解脱を得たならば、この他に解脱すべきものなど無いために、ただ止と観との二つを説くのである。
4.語注
- 処処の経の中に…たとえば求那跋陀羅訳『雑阿含経』の第464経、「尊者阿難往詣上座上座名者所。詣已。恭敬問訊。問訊已。退坐一面。問上座上座名者言。若比丘於空処樹下閑房思惟。當以何法専精思惟上座答言。尊者阿難。於空処樹下閑房思惟者。當以二法専精思惟。所謂止観」云々(大正2, P118中段)。もっとも、この経中では説者は初め仏陀ではなく、上座という名の上座(長老)である。阿難尊者は次に五百比丘の所で同じ質問をするが、皆が全く同様の答えをなした。そして阿難尊者は、仏陀の所に赴いてやはり同様の質問を繰り返したが、まったく同様の答えであった。師と弟子との言が完全に一致していることに驚き、賛嘆する尊者に対し、仏陀は答える。それは阿難尊者が質問した彼の上座も五百比丘も、皆が阿羅漢であるからだ、と。
この経典では、「止→観⇒解脱」「観→止⇒解脱」との二つの次第が説かれている。止観といっても、必ずしも止そして観と次第して修習しなければならないのではないことを明かしている。いずれにせよ「止観倶修」によってこそ人は阿羅漢になり得る、というのがこの経典の趣旨である。蛇足であるが、阿難尊者は釈尊存命中は阿羅漢になることが出来なかった。尊者が阿羅漢となるのは、仏滅後三ヶ月後のことであり、この時点で尊者は、これらのことについてわからない立場にあった。
また、同じく『雑阿含経』の第964経では、仏陀は「有二法。修習多修習。所謂止観。此二法修習多修習。得知界果。覚了於界。知種種界。覚種種界」(大正2, P247中段)と、やはり止観の修習によって人は悟りに至ることを説いている。→本文戻る - 比丘[びく]…「(食を)乞う者」を原意とする、サンスクリットBhikṣu[ビクシュ]またはパーリ語Bhikkhu[ビック]の音写語。もとはインドの出家者・遊行者全般を指して言った言葉であると云うが、仏教では特に、具足戒を受けた正式な男性出家修行者のことを意味する。→本文に戻る
- 阿蘭若処[あらんにゃしょ]…サンスクリットAraṇya[アランヤ]あるいはパーリ語Arañña[アランニャ]の音写語。元は単に、森あるいは林の意。もっとも仏教では、人里から遠すぎず近すぎず離れた森林・山間など、修行するのに適した閑静な土地のことを専ら言う。漢訳仏典の中では、時として練若[れんにゃ]あるいは蘭若[らんにゃ]と略称される。→本文に戻る
- 止観[しかん]…仏教の瞑想。止と観という二つの異なる瞑想法の総称。止は、サンスクリットのŚamatha[シャマタ]あるいはパーリ語Samatha[サマタ]の漢訳語。漢訳仏典の中では、しばしばこれを音写した奢摩他[しゃまた]という言葉でも表記される。観は、サンスクリットVipaśyanā[ヴィパシュヤナー]あるいはパーリ語Vipassanā[ヴィパッサナー]の漢訳語。毘鉢舎那[びぱっしゃな]という音写語で言われることもある。止と観との漢訳語は、それぞれ全く適訳と言え、そのままその瞑想内容を端的に表したものとなっている。『成実論』では、止観の功能をそれぞれ、止は遮断(一時的に煩悩を生起せしめざること)、観は断滅(煩悩を根絶して二度と生起せしめざること)と説いている。→本文に戻る
- 禅定[ぜんじょう]…禅は、サンスクリットDhyāna[ディヤーナ]あるいはパーリ語Jhāna[ジャーナ]の音写語。定は、その漢訳語。原語は、「明らめる」「知る」などを意味する√dhī[ディー]からの派生語で、「瞑想」から「思想」、「沈思」を意味する言葉。仏教では特に「深い瞑想の境地」、具体的には「(瞑想によって)強力な集中力を得た心の状態」を指して用いられる言葉。
説一切有部では、これに四禅八定と八つの段階、あるいは九次第定と九つの段階のあることが言われる。他に、例えば上座部では、色界・無色界の八つの心に、それぞれ禅に五つの段階のあることを説いている。この禅という心的状態に達するのは決して容易なことではなく、並々ならぬ精進が要求される。人はしばしば、瞑想中に得た多少の恍惚感・衝撃的経験をもって初禅を得たと勘違いする。
故に仏陀は、比丘たちに対し、「禅定を得たなどと嘘言してはならない」ことは勿論、「もし禅定を得たとしても、決して在家信者はもとより沙弥など具足戒を受けていない者に語ってはならない」と厳戒された。まれに出家者でありながら、「私は何時にこれこれの禅を得た」「これこれの尋常ならざる経験をした」などと世間に吹聴して回るものがあるが、それはまったく出家者として過失ある非法行為であり、実際に律で明確に禁じられている。
ちなみに、「禅」という漢字そもそもの意味は、「天子が位を譲ること」あるいは「天子が神を祀ること」で、まったく瞑想云々に関係するものではない。しかし後代には、禅という言葉が、支那由来の仏教思想全般、仏教の大きな流れのうちの一つを示す言葉にもなった。→本文に戻る - 散心[さんしん]…禅心でない、その対象がつねに移り変わる散漫した心。凡夫の普段の心。→本文に戻る
- 聞思[もんし]等の慧…聞・思・修の三慧のうちの聞慧と思慧。
三慧とは、仏の教えを聞いたことによって生じる慧、その理にしたがって考えた(思惟)ことによって生じる智慧、そして修めたことによって生じる智慧の、三つの智慧(優れて明らかな心の働き)のこと。『成実論』廿。
あるいはまた一般に、仏の教えはまずこれを耳にし、自ら(正しく)考え得心し、そしてこれを実践して確認していくことである、などとも言われる。そもそも、人にはわずかばかりであっても幾ばくかの智慧が、仏道に入るにあたって必ず必要である(さもなければ、初めにこれを「聞いた」としても馬耳東風となる)が、この循環を繰り返すことによって、聞き・考え・修める能力(智慧)が発展していく。→本文に戻る - 結[けつ]…煩悩。生死流転の世界、苦しみあふれる娑婆世界に結びつける因と成るためにかく言う。→本文に戻る
- 没…異本には泥とある。実際、泥としなければ意味がまったく不明となるため、現代語訳においてのみ、泥すなわち朱肉の意としてここでは読んだ。→本文に戻る
- 衆生[しゅじょう]…もろもろの生き物。意識あるもの。サンスクリットsattva[サットヴァ]あるいはパーリ語でsatta[サッタ]。有情[うじょう]との漢訳語もある。
仏教において生命の定義は現代のそれと異なる。すなわち、植物は仏教において衆生の範疇に入っていない。故に、仏教は輪廻転生を説くが、「植物に転生」などということは決して云われない。植物は生まれ育つものではあっても輪廻する存在ではない。ただし、植物が衆生のうちに含まれていないと言っても、動物や神霊など生命の重要な生活の場、あるいは人々の財産という限りにおいて大切にされる。→本文に戻る - 二辺[にへん]…極端な享楽主義と苦行主義の二つ。ただし享楽主義といっても、古代ギリシャで主張されたもので例えて言うとすれば、エピクロス(Epikouros)が主張したそれ(エピクロス主義)ではなく、キュレネ派の祖アリスチッポス(Aristippos)が主張したのに類するもの。苦行主義についても、それは釈尊の当時から行われていた、(煩悩の滅、智慧・涅槃の獲得にまったく資さないという点で、仏教からすれば)不合理な、インドにおける苦行に専念することを意味する。犬や牛のまねをして四つん這いで生活すること、炎天下に我が身をさらし、さらに四辺に火を焚いて耐えること等の類。釈尊はそれら二辺を自ら経験した上で、これらに親しむことを否定した、という経説にもとづいた理解を単純化させ、仏教においてはいかなる苦行も否定されるべきと誤解する者が実に多い。が、しかし、現在にまで伝わる仏教が説く修行や戒律には、(特に現代の?)人によっては、あるいは「極端な」禁欲主義・苦行主義と映じるものがあり、これを釈尊の教えに反する、などと批判する者がある。(そもそもまず苦行の定義が必要であろうが)しかし、実際には、それが涅槃・解脱、智慧の獲得に資する限りにおいて、仏教も少なからず苦行(Tapas[タパス]・Tapo[タポー])をその随所において説いている。
なお、二辺という言葉は、断見(因果応報ならびに輪廻転生を否定する思想)と常見(すべての事象の背後にはなんらか恒常不変の本体・存在があって、それは不滅とする思想)の、仏教からすると全く誤った二つの見解を意味する場合もある。→本文に戻る - 七浄[しちじょう]…戒浄・心浄・見浄・度疑浄・道非道知見浄・行知見浄・行断知見浄の七種。『成実論』巻二 法聚品第十八に、「七淨戒淨者戒律儀也。心淨者得禪定也。見淨者斷身見也。度疑淨者斷疑結也。道非道知見淨者斷戒取也。行知見淨者思惟道也。行斷知見淨者無學道也」(大正32, P253上段)と、それぞれ何をいうかを簡単に述べられている。→本文に戻る
- 八大人覚[はちだいにんかく]…小欲・知足・遠離・精進・正憶・定心・智慧・無戯論の八つ。『成実論』巻十四 善覚品第一百八十三に、八大人覚についての問答が展開している(大正32, P353中段)。→本文に戻る
- 四憶処[しおくしょ]…身念処・受念処・心念処・法念処の四つ。四念処あるいは四念住ともいう。ここより以下、いわゆる三十七菩提分法(『成実論』では三十七菩提助法)のそれぞれを、止と観とのいずれかに配当して理解することが行われる。→本文に戻る
- 四如意足[しにょいそく]…欲如意足・精進如意足・心如意足・思惟如意足の四つ。神通力を得る禅定を、その得るための方法によって四つに分類したもの。四神足ともいわれる。→本文に戻る
- 四正勤[ししょうごん]…精進(努力精励)を四つに分けたもの。あるいはその段階。すなわち、1.己の心身に生じている悪を停めるために勤めること。2.未来に己の心身に悪を生じさせないように勤めること。3.己によって未だ実現されていない善をなそうと勤めること。4.すでに己によって実現されている善をさらに増長させるよう勤めること、の四つ。→本文に戻る
- 五根[ごこん]…信・精進・念・定・慧の五つ。信を以て仏道修行の初めとし、精進によって悪を防いで善を修め、念によって我がなすところを観じ整え、定によって心を鎮め、慧によって解脱を目指す。また、信は慧に依って、それが妄信とならぬよう整えられ、精進は定に依って、それが行き過ぎぬようならされる。念は常に用いられる。→本文に戻る
- 力[りき]…五力[ごりき]のこと。五力は、五根のそれぞれをさらに発展、強力にしたもの。→本文に戻る
- 七覚分[しちかくぶん]…諸法を覚知するのに、智慧(菩提)に依ってする七つの方法。七菩提分[しちぼだいぶん]とも。すなわち、念菩提分・択法菩提分・精進菩提分・喜菩提分・猗菩提分・定菩提分・捨菩提分の七。このうち、念は止と観とのいずれにも用いられるものとしているものの、他のいずれの三覚分が止に、そして観にするかが明らかにされていない。注釈書の伝わらないことが惜しまれる。
七菩提分(七覚分)ならびに他の三十七菩提分について、『成実論』は、その巻二 四諦品第十七にて詳らかにしている。「念菩提分者。学人失念則起煩悩故。繫念善処繫念先来所得正見是名択法。不捨択法故名精進。行精進時煩悩減少心生歓喜故名為喜。以心喜故則身得猗是名為猗。身猗得楽楽則心定。是定難得名為金剛。得無著果断憂喜等故名為捨。是名上行。又不没不発其心平等故名為捨。菩提名無学智。修此七法能得菩提名菩提分」(大正32, P251下段)云々と。
→本文に戻る - 八道分[はちどうぶん]…一般には八正道という。仏教における修行の根本。すなわち、正見・正思・正語・正業・正命・正精進・正念・正定の八つ。ここでは何を以て、戒とし止とし観とするのか明瞭でない。
しかし、ここで戒・止・観を、三学の戒・定・慧に置き換えてみた場合、このような説のあることが知られる。『中阿含経』巻五十八「晡利多品法楽比丘尼経」(第210経)では、正語・正業・正命を戒学に、正念・正定を定学に配当し、正見・正思・正精進を慧学としている(大正1, P788下段)。これが数としては『成実論』の配当に一致する。また、これは大乗の典籍であるが『瑜伽師地論』も同様に説いている。これだけでは根拠不十分かもしれぬが、この阿含経説をもって、ここでの『成実論』と同様のものであると見て良いであろう。
しかし、参考までに、小乗二十部のうち唯一現存している分別説部大寺派(上座部)の教学を見れば、八正道のうち正語・正業・正命を戒学に、正精進・正念・正定を定学に配当し、正見・正思を慧学としている。これは、分別説部無畏山寺派も同様の説を採っていたことが『解脱道論』因縁品によって知られる。八正道を三学に配当するに、上の如き諸説あったことが知られるが、結局問題とされるのは正精進をいずれに配当するかということであったようである。
ついでながら、これはまったく蛇足となるが、支那は隋代の大学僧、浄影寺慧遠による『大乗義章』では、正語・正業・正命を戒学に、正念・正定を定学に配当し、正見・正思を慧学とし、正精進は三学すべてに共通するものと位置づけている。→本文に戻る - 貪[とん]…飽くことなく欲求し続ける心の働き。三つの根本煩悩、「貪・瞋・痴」の三毒の一つとして数えられる。サンスクリットあるいはパーリ語ではLobha[ローバ]。貪欲[とんよく]・貪愛[とんあい]。渇愛[かつあい](Tanhā[タンハー])の別の謂いでもある。→本文に戻る
- 無明[むみょう]…モノの真なるあり方を認識できない心の働き。真理について盲目である心の働き。無智あるいは痴とも。サンスクリットでAvidyā[アヴィドヤー]、パーリ語ではAvijjā[アヴィッジャー]。煩悩の根本、三毒の主幹。すべての生存における苦しみの元凶。→本文に戻る
- 心解脱[しんげだつ]…心が貪欲から自由となった状態のこと。貪欲に縛られない、自由な心の状態。→本文に戻る
- 慧解脱[えげだつ]…無漏の慧によって、貪欲だけでなく瞋恚と無明(痴)との煩悩を断滅して自由となった状態。もはや再び退転することのない、阿羅漢の解脱。
もっとも、これは余談であるが、大乗では、慧解脱は煩悩障[ぼんのうしょう]を断じたものではあるが、未だ所知障[しょちしょう]を断じ得ていないとしてこれを一段低い解脱、小乗(不完全な教え)の解脱であると一般に見なしている。故に、煩悩障・所知障の双方を断じることをもって、最高の悟り・解脱であるとしている。→本文に戻る
4ページ中1ページ目を表示
解題・凡例 |
1 |
2 |
3 |
4 |
原文 |
訓読文 |
現代語訳
メインの本文はここまでです。
現在の位置
このページは以上です。




